子どものぐずりが増えてきて、些細なことで癇癪が起こる。
つい、イライラしていまい怒鳴ってしまったり、なんでうちの子はこんなに毎日毎日ぐずるんだろうと悲しくなることもありますよね(;_;)
我が家の現在9歳になるひといちばい敏感な気質(HSC)をもつ長男も、いまだに『ぐずり』『癇癪』が多い子どもです。
毎回同じ方法で『ぐずり』『癇癪』が落ち着くわけではありませんが、幾度もの『ぐずり』『癇癪』を経験した私が癇癪の芽である『ぐずり』が増えたら注意したい点と、対応方法についてご紹介します。
最近子どもの『ぐずり』が増えてきたと感じたときに、事前に対策を講じることで『癇癪』に至らず子どもの気持ちが安定する場合があります。
お子さんの『ぐずり』『癇癪』でお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。
ぐすりの原因は、不快?不安? 言語化する手伝いをしよう
『癇癪』は起こってしまうともう何も耳に届きません。ただただ身の安全を確保しつつ落ち着くのを待つしかありません。
そうなる前に対策を講じ、子どもが『癇癪』を起こさなくても済むような状態にもっていくことが重要です。
子どものぐずりが増えてきたら、『癇癪』の予兆…爆発する前にガス抜きさせることが何よりも重要だと感じています💪
『ぐずり』の原因となっているモヤモヤの原因を探るステップを順を追ってご紹介します。
なるべく機嫌のよい時を選んで2人きりになる
『ぐずり』が増えてくると、文句が増え機嫌の悪い時間が増えます。
不機嫌モードの時に色々聞き出そうと試みても、子どものイライラを助長する恐れがあるため、なるべく刺激せず、ママはとにかく落ち着いたトーンで(普段より声のトーンを上げるとなお良い←私は普段声が低めなので、よく息子に不安を与えるようです…)共感と相槌に徹します。
一日の中で、機嫌のいいタイミングが来たらチャンス!!!!なるべく2人きりになれる場所へ行きしょう。
ママはとにかく落ち着いて、安心感を与えるトーンでヒアリング
2人きりになったら、子どものモヤモヤの原因を言語化する手伝いをします。
『ぐずり』『癇癪』を起こしている本人も、なぜ自分がこんなにイライラするのか、不快が気持ちに襲われているのか…理由がわからないのです。
そのどうすることもできないモヤモヤを、一番近くですべてを受け入れてくれるママに『ぐずり』『癇癪』という形で発散させているのだろうと思います。
モヤモヤの原因が何かを子どもとの対話の中から探し、言語化するお手伝いをするのがこのステップです。
・どこか痛いところや、具合の悪いところはないか
・友人関係で困っていることはないか
・学校の先生のことで困っていないか
・授業で躓いていることはないか
などなど。落ち着いて子どもと対話することで、少しずつ本人の口から困っていること、気になっていることがでてくることがあります。
すぐにモヤモヤの原因が解決できなくても大丈夫
うまく言語化できず、モヤモヤとなっていたことが子どもの口から漏れて来たら、
ママは「そうだったんだね。」「不安だったね。」「話してくれてありがとう」
など、共感と感謝を伝えてあげましょう。
ひといちばい敏感な子どもは、ひといちばい不快や不安を感じている子どもでもあります。
何よりもママに安心を求めているのです。
モヤモヤの原因となっていたことが分かったら、親としては一刻も早く解決してあげたいと思いがち…
ですが、学校での友人関係など親が口を出しすぎず様子をみることが必要な場合もあります。
この時点で根本的な解決には至らずとも、子どものモヤモヤの原因を本人の力で言語化できたこと、ママが自分のモヤモヤについてわかってくれた、そのことで子どもが安心しぐずりが減ることに繋がります。
まとめ
『ぐずり』『癇癪』は起きていないとき、機嫌のいい時にどう対応するかが一番重要です。
ついつい、ぐずっている時や癇癪を起こしている時にどうしよう(;´Д`)となってしまいがちですが、機嫌のいい時にこそ手を打つのです!!!
『ぐずり』『癇癪』には必ず原因になっている不快や不安な気持ちがあります。
ぐずっている本人も、モヤモヤの原因が何なのかわからずもがいているのです。
機嫌がいい時=モヤモヤ解決のチャンス!
モヤモヤの原因がわかったら、日々の生活の中でフォローできるものは手伝い、見守るところは見守りつつ、時々声をかけて気にかけていることを伝えましょう。
私自身、ついこの事をつい忘れてしまい、『癇癪』が発動し手がつけられなくなることもしばしば…
いいのです。親も人間です。日々に翻弄され気付けないことだってあるのです。
自分を責めることなく、次こそは早めに手を打つぞ!と前を向いて今日も一緒に育児に励みましょう💪
最後まで読んでいただきありがとうございました😁
私たちはもう十分に頑張っている!!!
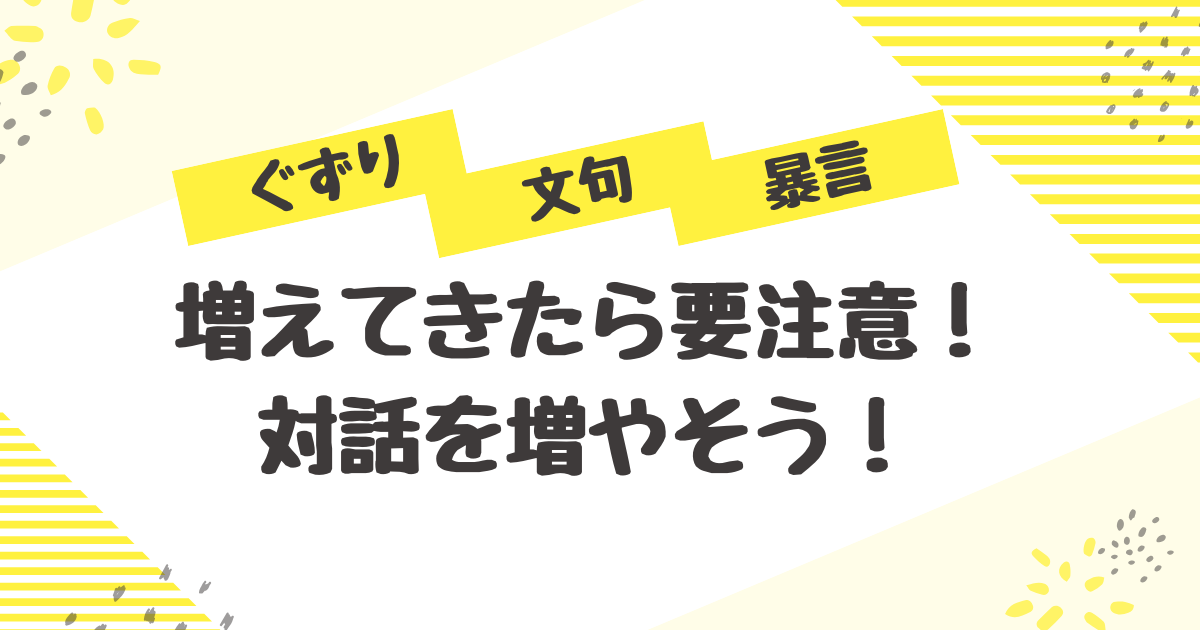

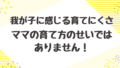
コメント